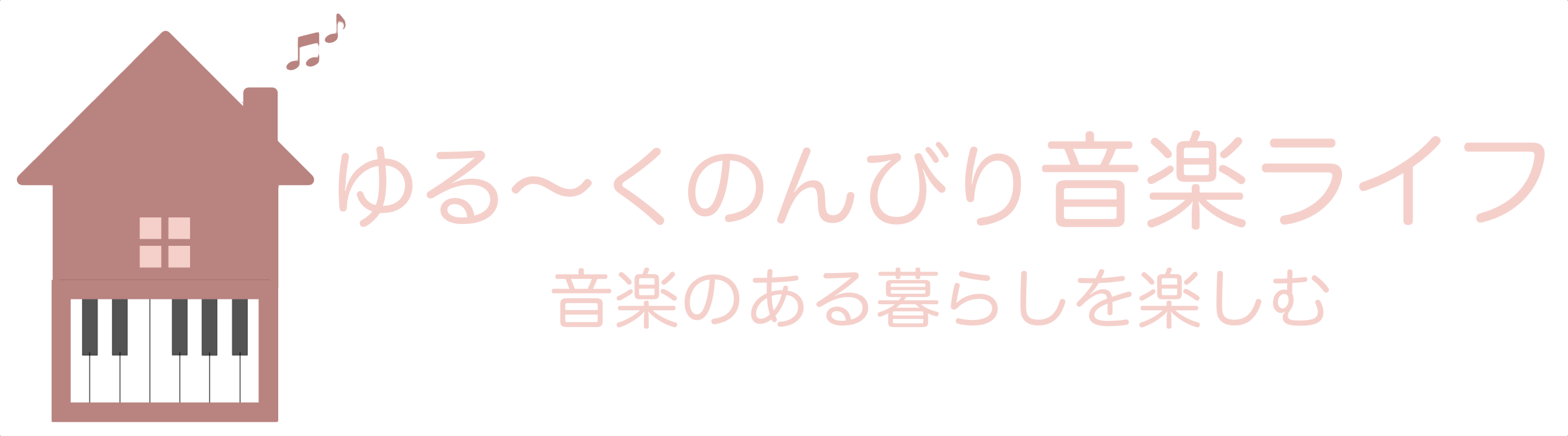なぜポーランドだけが心に残ったのか|キュリー夫人とショパンをめぐる記憶
子どもの頃、何気なく手に取った伝記の中に、キュリー夫人がいた。
物語としての筋や成果よりも、断片的な場面が、そのまま今も記憶に残っている。
寒さの厳しい環境で、十分とは言えない条件の中、それでも学び続けている姿。
そして、あるとき授業が突然、裁縫の時間に切り替わる場面。
その唐突さが、学ぶという行為の不安定さとして、強く印象に残った。
知識は、いつでも当たり前に許されるものではない。
そんな空気が、子どもなりに伝わってきた気がする。
当時、彼女がノーベル賞受賞者だということは知らなかった。
偉業を成し遂げた人物としてではなく、ただ学びに向かい続ける人として、心に残っていたのだと思う。
大人になってから、断片的に事実を知るようになった。
夫の死の背景や、私生活に関わる出来事。
研究がもたらした成果と、その先に連なっていく影。
子どもの頃に抱いていた尊敬の像と、静かに食い違うものが、少しずつ重なっていった。
尊敬が崩れた、というより、単純ではいられなくなった。
知ってしまったあとでも、尊敬の感情が残っていることは、正しいのかどうか、自分でもよく分からない。
知が光を放つことと、その影を引き受けることは、切り離せない。
頭ではそう理解しながらも、感情の整理は簡単ではない。
割り切れなさだけが、静かに残った。
旅行先として、行きたい場所を考えるようになったのは、ずっと後のことだ。
理由を並べて現実的に考えていく中で、多くの候補は自然と外れていった。
それでも、なぜかポーランドだけは外れずに残った。
強い動機があったわけではない。ただ、消えなかった。
振り返ってみると、そこには共通した感覚があったのかもしれない。
尊敬や帰属、価値といったものが、きれいに一つにまとまらないまま残り続ける感じ。
その少し居心地の悪い状態が、ポーランドという場所と、どこかで重なっていた。
その感覚の中に、ショパンという存在が入り込んでくる。
祖国を離れ、亡命し、パリで生きた作曲家。
お墓はパリにあり、心臓はポーランドに戻された。
その事実は、整いすぎているようで、同時に、どこか落ち着かない。
国と個人、生と死、帰属と選択。
ポーランドとパリが分かれていることは、悲劇とも美談とも言い切れない。
ただ、そうなっている。
その分断のあり方が、説明を拒むように、静かにそこにある。
キューリー夫人の記憶と、ショパンの存在。
知と芸術、光と影、尊敬と違和感。
どれも整理しきれないまま、重なって見えている。
ポーランドという場所が今も外れずに残っている理由を、無理に言葉にする必要はないのかもしれない。
理解しきれないものを、理解しきれないまま置いている。
今も変わらず、ここにある。