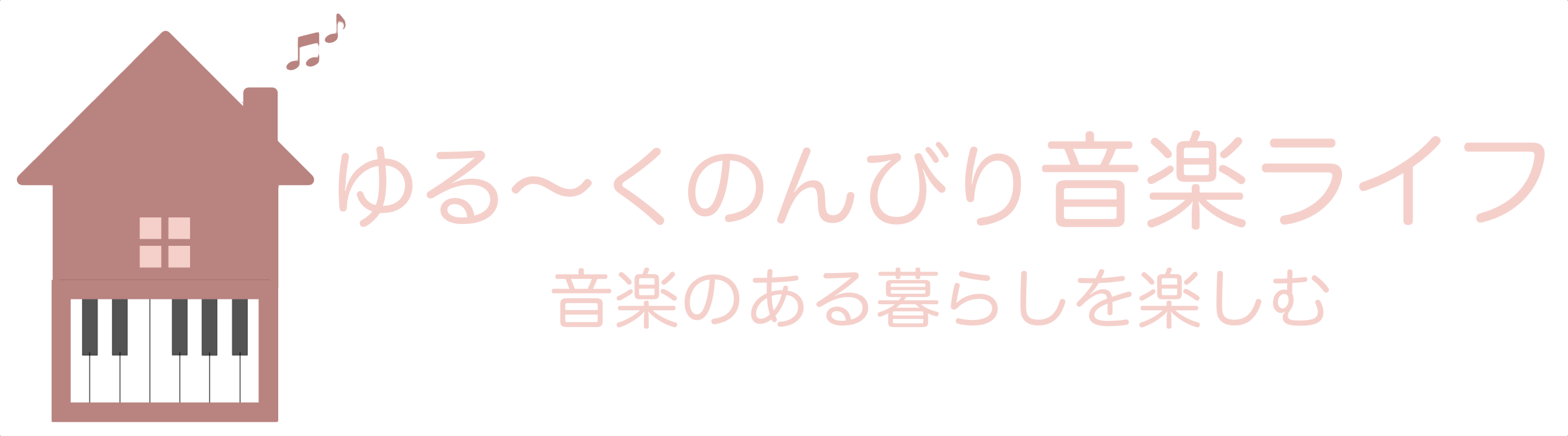映画『旅と日々』――静けさにそっと寄り添う時間
ひとつひとつの風景が、しんとした余韻をまとった作品だった。
観終わったあとに残ったのは、言葉で説明する“感動”ではなく、深い呼吸のあとに訪れるような静けさ。
目的や意味を求めがちな日常からいったん距離を置き、「何となく」の手ざわりを思い出すための余白をもらった気がする。
作品概要(ネタバレなし)
『旅と日々』は、旅先を舞台に“何も起きないように見えて、ひとりひとりの時間が静かに動いていく”物語。原作はつげ義春の短編2作品で、監督は三宅唱。
脚本家の李(イ)が、旅館での出会いや風景を通して、言葉に縛られていた自分を少しずつほどいていく。海、雪、風……自然が登場人物のように寄り添い、派手なドラマを伴わずに心の隙間をすくう静かな映画。
観て感じたこと
海のシーンは、まっさらな余白みたいだった。
ぼーっと海を眺めるだけなのに、小笠原や与那国の海がふっと思い浮かぶ。何もしない時間がどれほど豊かだったかを、久しぶりに思い出した。
対照的に強く惹かれたのが、雪の描写。
尋常じゃない量の雪が積もる風景に、大雪警報の中で山形の温泉へ向かった日の記憶が蘇る。湿った静けさと、真っ白な世界に閉じ込められた感覚。作品の雪景色には、妙な馴染みがあった。
シム・ウンギョンが正座でご飯を食べるシーンも印象的だった。
正座って外国の方には大変なはずなのに、そのぎこちなさがむしろ作品の“生活感”になっていた気がする。
そして、堤真一の存在感。
「やまとなでしこ」の頃のイメージを残しつつ、いい意味で年齢を重ねた“イケおじ”。いびきのシーンでは客席から小さな笑いが漏れた。
宿の食事も心に残った。
ご飯、味噌汁、お漬物。
それだけで十分だと思わせてくれる、生活の芯のような組み合わせ。思わず「これだよね」と呟きたくなった。
ただ、音楽だけは少し気になった。
自然音が多い作品だからこそ、打ち込みの質感がところどころ浮いて見える。
……あれは意図的だったのかな?と、ちょっと考えてしまった。
心に残ったシーン
海辺の若いふたりの、あの気まずい会話。
演技が巧いとか下手とかではなく、「本当にこういう瞬間ってあるよね」と思わせる生々しいぎこちなさがあった。
岸壁のシーンでは、伊豆のイガイガ根が頭をよぎった。
あんな場所、普段は立ち入らないはずなのに、海の匂いが一気に近くなるあの感じが妙に懐かしい。
車のフロントガラスについたゴミを取る動作にも、脚本の巧さを感じた。
ただの仕草なのに“生活”が宿る。
脚本って、音楽でいう編曲に近い気がする。
どこを切り取り、どう並べるか。その選択ひとつで、同じ物語でもまったく違って見える。
この映画が語りかけてくるもの
『何しにきた?』
『何となく』
このやりとりが、妙に心に残った。
観光地に行くと「あそこも」「ここも」と予定を詰め込みがちだけど、「何となく」で動くことって、実は一番強いのかもしれない。
今はどこにいても“言葉”だらけだ。
説明や意図や目的が押し寄せてきて、その洪水から離れたくなる瞬間がある。
旅に出ても、何もしなくても、つい“何かを得なきゃ”と考えてしまう癖もある。
教授の遺品のカメラを手にした主人公が、日常のすきまに小さな物語を見出していく姿には共感した。
誰にも物語があり、誰もが主人公。
脚本によって見え方が変わるのだとしたら、私たちの毎日も“どんな演出で見るか”で世界の景色が変わるのかもしれない。
まとめ
全体として、劇的な感動はなかった。
けれど、その“なさ”がこの映画の魅力だったと思う。
派手なドラマではなく、静かに味わうタイプの作品。
じわっと沁みるような、ゆっくり染み出すような余白があった。
こういう系、私は好きだ。