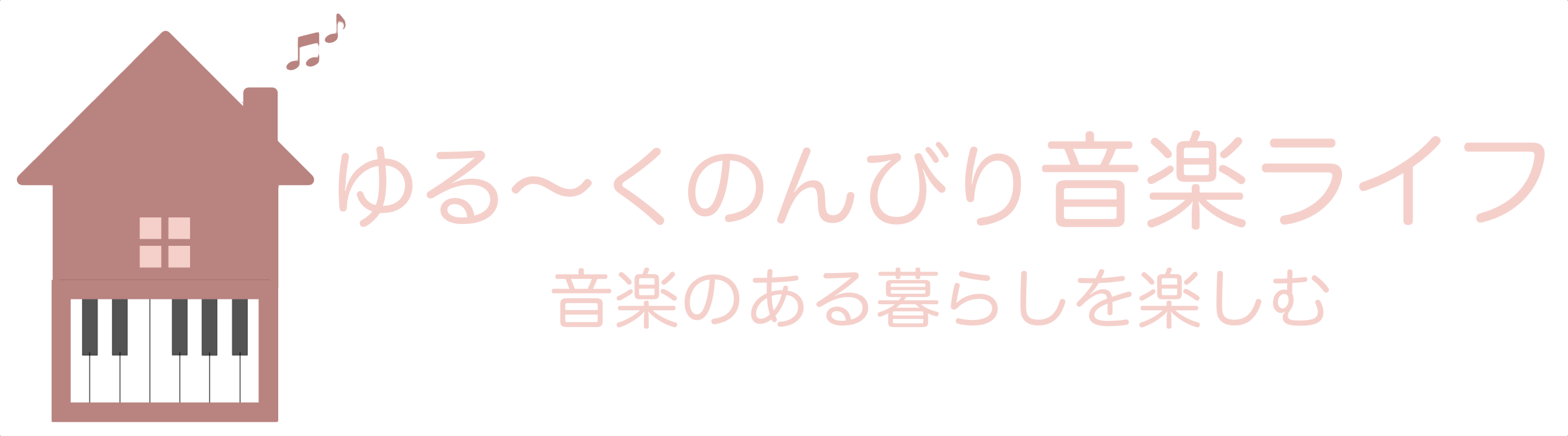『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』を観て ──「シェルブールの雨傘」の音楽が忘れられない理由
――天才は、だいたい扱いづらい
正直に言うと、この映画を観ようと思った理由はかなり単純だ。
『シェルブールの雨傘』が好きすぎるから。
理由を言葉にしろと言われると、うまく説明できない。
ただ、感情よりも先に身体が反応してしまう音楽がある。
子どもの頃から、あの旋律を耳にすると理由も分からず涙が出てくる。
切ない。美しい。……それ以上の言葉が出てこない。
語彙の乏しさが恥ずかしいが、事実なので仕方がない。
作曲者がミシェル・ルグランだということも、もちろん知識としては知っていた。
けれど「知っている」で止まっていた。
そんなとき、たまたまこのドキュメンタリーの予告を観た。
――あ、これはちゃんと向き合うやつだ。
そう思って、劇場へ足を運んだ。
天才は気難しい? それとも、ただの厄介な人?
まず引っかかったのは、彼の人との接し方だった。
指揮者やオーケストラの奏者に対する言動が、まあ強烈。
才能がある人は多少のことは許される――
そんな空気が、画面越しにもはっきり伝わってくる。
昔なら「天才だから」で済んだのかもしれない。
でも今だったら、◯◯ハラと呼ばれてもおかしくない場面がちらほらあって、
こちらが勝手にハラハラしてしまった。
ただ、この映画はそこを美化しない。
天才=聖人君子ではないという事実を、淡々と映す。
その姿勢は、むしろ誠実だったと思う。
どんなに扱いづらくても、
あの切ない旋律を生み出した人物であることは、否定しようがないのだから。
弾いている、のではなく「何かが起きている」
特に印象に残ったのは、ピアノ演奏のシーンだ。
練習風景は、正直、どこか親近感がある。
ピアノを弾く人なら、たぶん誰でも見覚えのある光景だ。
ところが本番――
ステージやレコーディングになると、空気が一変する。
弾いている、というより
「音が身体を通って噴き出している」感じ。
スイッチが入ったのか、神様が降りてきたのか。
うまい言葉は見つからない。
ただ、心ははっきり震えた。
どうしたら、こんな演奏になるのだろう。
いったい、演奏者の内側で何が起きているのだろう。
その姿は、晩年の坂本龍一と、どこか重なって見えた。

クラシックとジャズ、洗練されたブレンド
ミシェル・ルグランは、パリ国立高等音楽院でクラシックを学び、
同時にジャズを深く愛した人だった。
その二つが、彼の中で洗練されたブレンドとして結実している。
映画には、錚々たるジャズ・ミュージシャンの名前が次々と出てくる。
中でも、ディジー・ガレスピーの名前が出てきたときには、思わず姿勢を正した。
私自身も、彼の音楽から少なからず影響を受けてきたからだ。
人が人に影響を与え、
その影響がまた次の音楽を生む。
その連鎖を目の当たりにすると、気持ちが引き締まる。
クラシックとジャズのブレンドといえば、
私がすぐに思い浮かべるのはニコライ・カプースチンだ。
同じブレンドでも、フランス人とロシア人。
気質も、色も、まるで違う。
その違いが、たまらなく面白い。
同じ材料でも、料理人が違えば味は別物。
音楽も、まさにそうなのだと実感する。
知らなかった、という事実に打たれる
驚いたのは、
「風のささやき」や「キャラバンの到着」も、
ミシェル・ルグランの作品だったと知ったことだ。
さらに、「こんなにも多くの作品を?」と、思わず呆然とした。
私は、ほとんど何も知らなかったのだ。
でも、その事実は嫌ではなかった。
むしろ、世界がぱっと開けた感覚があった。
知らない音楽が、まだこんなにある。
そう思えたこと自体が、この映画のいちばんの収穫かもしれない。
帰宅してすぐ、
「The Summer Knows」の楽譜を購入した。
少しずつでいい。
自分のレパートリーの中に、彼の音楽を迎え入れていこうと思う。
ちなみに、私自身が長年惹かれ続けている
『シェルブールの雨傘』の旋律については、
実際にピアノで向き合った記録も残している。

天才はやっぱり、だいたい扱いづらい。
けれど、その厄介さごと受け止めてなお、
音楽は、ちゃんとこちらの世界を広げてくれる。
それで十分だ。